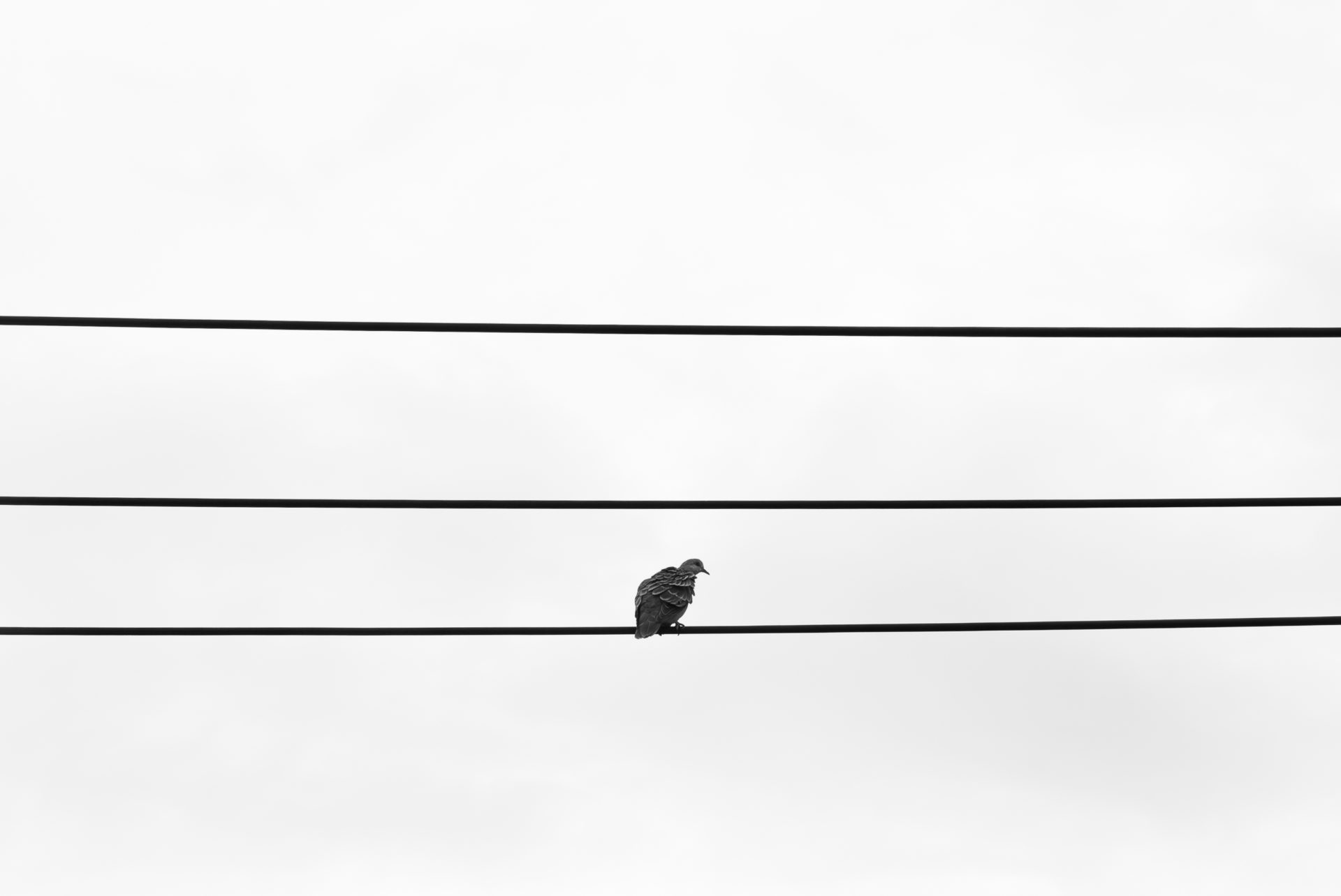studioBAKER Novel「Directors Chair」23
スタジオベイカー短編小説「ディレクターズチェア」
第23話「椅子との決別」
映画館のホールには、深い沈黙が満ちていた。
フィルムの上映が終わり、光田浩一はその余韻を一人で受け止めていた。
スクリーンは消え、映写機の音も止まった今、耳に届くのは自身の心音だけ。
足元には、佐伯監督が遺した最終フィルム。そして、中央には例の二脚の椅子が並んでいる。
「……終わったのか」
光田は呟いた。しかし、胸の奥では別の声がささやいていた。
「これは、終わりではない。次の記録者を迎える準備にすぎない」
彼は気づいていた。椅子に刻まれたイニシャルと日付、佐伯監督の未完のシナリオ、そして“影”。
それらが一つの意志のもとに動いていることに。
だが、果たしてその意志に従うことが“完成”なのか?
夜が更けた頃、渡辺沙織が映写室を訪れた。
「光田さん……帰ってなかったんですね」
「……まだ、やるべきことがある」
彼女は一歩進み、椅子を見つめた。
「この椅子と、もう終わりにしませんか?」
その言葉に、光田は静かに目を伏せた。
「この椅子に、俺はずっと引き寄せられていた。でも、今ならわかる。これを映し続ける限り、何かが終わらないまま残り続けるんだ。」
沙織がそっと尋ねた。
「じゃあ、どうするんですか?」
「燃やす」
その言葉に、ホールの空気が一変した。まるで、椅子そのものが反発したかのように、背もたれが微かに軋む音が響いた。
光田は構わず続けた。
「この椅子が、記憶と影の交差点だったなら――記録者としての役目はもう終えた。ならば、ここで終わらせる」
その夜、映画館の裏手、古い中庭にて。
光田はスタッフ数名とともに、二脚のディレクターズチェアを運び出した。
誰も言葉を発しない。
皆、理解していた。これは撮影でも演出でもない、儀式なのだと。
火を灯す準備が整ったとき、光田は最後に一つだけ椅子の背を撫でた。
「……ありがとう。俺を導いてくれて」
その手が離れた瞬間、椅子の隙間から何かが滑り落ちた。
光田が拾い上げると、それは佐伯監督の手帳の切れ端だった。
「椅子は私の記憶を記録する装置だ。しかし、私の意志で終わらせることはできない。
次の者がそれを理解し、決断するまで、この椅子は待ち続ける」
光田は目を閉じ、深く息を吸った。
「ならば、ここで終わらせる」
彼は火を灯した。
炎がゆっくりと椅子を包む。
最初は静かだった火が、椅子の木材を噛むように音を立て始める。
まるで、長年記録し続けてきた記憶が、煙とともに空へ還っていくようだった。
光田の脳裏に、佐伯監督の声が最後に蘇る。
「影を撮ることはできない。だが、影を意識することで、人は初めて光を映す」
その言葉が、今なら理解できる気がした。
炎がすべてを焼き尽くした後。
灰となった椅子の中央に、一本の釘だけが残っていた。
光田はそれを手に取り、静かにポケットにしまった。
それは、記憶の“印”だった。二度と戻らぬものを、自分の中に留めておくための――。
数日後、光田は映画の編集室にいた。
フィルムはすべて整えられ、音も調整された。
そして、最後のフレームに、一行のテロップを加えた。
「監督:佐伯謙一郎/光田浩一」
スクリーンにその名前が並んだとき、ようやくこの映画は“完成”したのだと感じた。
影との対話、椅子との共鳴、記録されたすべての記憶が、今ここで終わる。
いや、終わらせた。
光田は椅子から立ち上がり、編集室の電源を落とした。
もう、あの椅子はない。
もう、あの“声”も聞こえない。
だが、この映画は生き続ける。
記録として。
そして、誰かの記憶を揺さぶる“物語”として――。
(最終話へつづく)
(文・七味)